〔20200615〕第9回 人間と言語② 新しいタイプのことば――独り言と内言
〔20200615〕第9回 人間と言語② 新しいタイプのことば――独り言と内言
《お知らせ》(再録)
◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、
https://kyouikugenron2020.blogspot.com/
に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。
◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。
送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。
bukkyo.bukkyo2017@gmail.com
編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。
「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。
また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。
なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。
あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。
《みちくさ》
今回はお休み。
《第8回講義へのコメントより》
【言語習得と子どもの発達段階】
今回の授業で新たに発見したことは、1歳半~3歳までのことばの発達は自然発生的であり、4~5歳のことばの発達は自然発生的ー反応的形成といえるということだ。私は、 1歳半~3歳のことばの発達も大人のことばの影響がほとんどであると思っていた。喃語も話せないようなときからの大人の声掛けや話しかける言葉から学んでいると思っていた。しかし、実際はそうではなく、子ども自身が周囲の環境から取り出しているのだと分かった。だから、「ワンワン」というような語を発したとしても、動物全体に対してその語を使ったりするのかなとも考える。また、 4~5歳は大人が使う言葉の影響を受けて、「黄色い花やね~」などというから、色+「い」をつけるものだと思って、「ピンクい花」などというのだと思うと、子どもはある意味感じ取り方や自分なりの解釈がすごいと感じた。
〔言語習得の主軸が子どもの発達段階に応じて変化していく、という観点が重要だと思います。もちろん、これは言語習得だけではありません。思考や情動、想像などの心理機能の変化もそうです。〕
【初語と意味の般化】
今回の授業で取り上げられた初語について、一つの語が意味する範囲が大人が考えるものよりもとても広いことが分かった。今まで、例に挙がっていたワンワンで言えば犬やその他の犬に似た動物を表すと思っていたが、コンドルやキリンのこともワンワンと呼んでいたことにはとても驚いた。さらに、カモを表すウガーはミルクやワインなどの液体、鳥の絵のコイン、コインに似た小さく丸く光るもの、など連想されるものがそのことばの意味の範囲になることがわかり、初語は大人が予想できないとてもおもしろいものだと感じました。
第八回の授業より、初語は過度に拡張使用されていることを知った。初語は「ワンワン」などの音声をあらゆる動物に置き換えて言うことは知っていたが、液体やコインなど大人では結びつかないような発想を持っていてそれが初語として現れることを知り驚いた。何らかの主観的印象の軸に基づき結びつけられ、集合しひとつのグループとなる。そしてそれらが大人の発語には主観的意味が込められているからこそ子どもの初語は拡張使用されていることがわかった。これらの拡張された初語を大人は「間違っている」と指摘するのではなく、「そうだね、きりんさんいるね」などと返すと子どもは自分の発言が理解されて、やりとりの楽しさを知り、そこからことばが育っていくと思った。また、「ママ」などの初語にもお腹が減ったことや眠いなどといった意味も含まれ、それらの思いが通じ合うことで乳児はことばの必要性を実感していくと思った。
新たに発見した考え方は、子どもがよく使うワンワンなどの初語はそれに似たものだけではなく、似ていないものや全く別のものにまで使われていたことだ。
従来の自分の考えは、例で言う「ワンワン」と言う言葉を、イヌだけではなくサルやネコなどでもこの時期の子どもは使うとほかの授業で学んだ。教育原論の第8回を受けるまで、「ワンワン」はイヌに似たような動物などに言うと思っており、似たものにしか使わないと思っていた。しかし、カモを「ウガー」と呼ぶ子どもの例で、液体や鳥の絵の描いたコイン、さらにはそのコインに似たものまで「ウガー」と読んでいたことが自分の中で驚きだった。カモのような生物だけではなく、自分がカモ(もしくはカモに似ているもの)と一緒の場面で見ていたもの(ここでは池やコイン)も同じようにその子にとって同じ場面で見たものだから「カモ」であって、「ウガー」と呼んでいたのかなと思った。その仮説が正しいのかわからないので、本当の意味でカモみたいなものと全く関わりのないものにも「ウガー」と呼ぶことがあるのか気になった。
似たもの(ワンワンなら他の動物)には使うという考えだったが、似ていないものにも使われているという考えを学び、自分にとって新しい考え方の発見だった。
【周りのことばを取り出す】
『ことばの発達において中心となるものは、大人がどのように子どもに教えたかではなく、「子ども自身が周囲の環境から取り出すこと」にある。』ということを新たに学びました。これまで、子どものことばの発達は親や周囲から発せられることばの全てに影響を受けると思っていたので、周囲の環境をもとに子ども自身が「取り出す」ということには新しさを感じ、大変驚きました。また、“幼稚園(保育園)に行きだしてから汚いことばを使うようになった。”という話をよく耳にするのですが、これも、子ども自身がそれぞれの環境にあることばの中からわざわざ汚いことばを取り出しているということでしょうか?もしそうなのであれば、なぜ子どもは、大人からみれば汚いとされることばを取り出す傾向にあるのか不思議に思います。
【子どものことばの主観的側面について】
1歳代の子供が発する初語、例えば例でも上がっている「ワンワン」は子どもの個人の主体的側面をよく表しているということが今日、新しく知った。その「ワンワン」という言葉の中に何種類もの動物が含まれていたり、その他のものにおいても含んだりするということは子どもの中で大人のようなはっきりとした区別や認識はないけれど、ある程度どういったものなのかを理解しているという理解につながることが分かった。つまり、子ども自身の中、子どもが主体となって、慣用の意味範囲を超えてグループ化していることになる。これは子どもが見たもの、経験したものの印象からきていて、大人が思っているよりもより想像力が豊かで、優越している部分だと思った。
大人になるにつれて、「これはこれだ」といった固定観念に縛られる世界が見えてきて、細かい認識があちこちに散らばっている。しかし、その状態から差別や偏見などといったものにつながっているのではないかと思った。だからこそ、慣用の意味範囲を超えての理解の仕方、関連なき関連性を考えていくことはとても重要だと思った。
〔大人のことばにおいても主観的側面があります。これは、語義という客観的側面によってコミュニケーションが可能になるとともに、この語義と密接な形で意味という主観的側面がくっきりと現れてきます。これについては、第13回講義で考えてみたいと思います。〕
【いわゆる英才教育について】
今日の授業で知ったことは、「子どもが通過する諸段階の順次性、子どもがとどまる各時期の長さは、母親のプログラムによってきていされたものではなく、基本的には、子ども自身が周囲の環境から取り出すことによって規定されている」ということです。まだことばが完全に形成されていない3歳未満の幼児は、大人にどう教えられたかによって成長が左右されると思っていました。
教育方法に悩む親が多いと聞きますが、親が我が子に完璧を求めて、まだこのことばが話せない時期から英才教育を施していてもあまり意味がないのでしょうか。
他人のプログラムではなく、自分自身でつくったプログラムに沿って成長しているのは、面白いと思いました。また、他人の考えや思惑にに影響されないことは、ある意味すごいなと思いました。
【語の意味は固定的でない】
私が今回の授業で新たに発見した点は、初語のもつ意味は多義的であり、その意味は固定的ではなく、たえず動いているということです。たその動きの落ち着く先は、初語の意味が分化し、慣用に近づくということです。村田さんの観察の例にもあるように、「ンマ」=ウマ、その後「ンマ、オンマ」を経て「オンマチャン」=ウマというようにたえず動いていることが分かりました。もちろんこれはその子の記録なだけで全ての子には当てはまりませんが、どの子もこれに類した「語の般用」が見られ、その語は運動して1歳代を多して慣用の方向に分化しているということが発見できました。
今まで私は、初語とは固定的で、初語の後にはすぐに話せるようになるのかなと思っていました。先程の例で考えてみると、今まで私は、ンマ=ウマだけでその子の中では完結し、ンマの後にオンマチャンなどと変動はせずに、いずれそのままの流れで話したりできるようになると思っていました。
しかし、今回の授業を通してその意味は固定的ではなくたえず動いていることが理解できました。そして、多様な意味が固定的な意味へと変動していくのは初語だけに見られる特徴であるということも分かりました。
〔ある意味では、語はそれを使う人の年齢がどうであろうと固定的でないのですが、しかし、年齢によって固定性は異なっています。1歳代の初語は固定性の小さいものだといえますが、そこから、自己意識が形成され始める13歳の危機までの時期は、固定性が大きくなっていくと考えられ、自己意識がしっかり形成されると、固定した意味である語義をもとに個人的な意味が豊かになり、そこから語義も変化を遂げる、というように変動的になると考えられます。つまり、図式的に言えば、変動的→固定的→変動的というような特徴を持つように思われます。〕
【「ワンワン」の語の起源について】
特に今回初めて知ることが多かったのは子どもの初期のことばの発達である。「ワンワン」という初語について私は最初から犬のことだけをさしているのだとずっと思っていた。初語の(有意味語)と意味の般化の部分で「ワンワン」ということばを動物園でありとあらゆる動物に言ったといったのには驚いた。はじめ言語心理学者の言っていた、「ワンワン」(初語)という動物語に限っても6種類の動物を表すという部分を読んでどういうことであるか疑問に思っていたのだがこのなんの動物にも「ワンワン」といってしまう子どもの話を読んで納得することができた。
「ワンワン」の話を考えていてひとつ思ったことがあり、質問します。私は「ワンワン」というのは子どもが自分で犬の鳴き声を聞いて自ら「ワンワン」と言い出すものであると考えていた。それゆえ上記の6種類の意味を持つという部分の意味を理解することができなかったのだが、「ワンワン」というのは大人からの働きかけで子どもが発する言葉なのでしょうか。さまざまな意味をことばの初期の発達段階でもつということは自分で考えて発していないと考えることはできるのだが、自然と発する子どももいるのではないかと考えた。
〔「ワンワン」は子どもの初語であるとともに、育児語として大人も使っている(これは犬という意味で)、犬の鳴き声と大人の育児語との双方が起源ということになりましょう。〕
【統語論(シンタックス)について】
初期のことばの講義を受けて新たに発見した事実は、統語論についてである。語が文に構成されるときの規則を表しており、シンタックスとも呼ぶ。統語論は、日本語だけでなく語順を中心とする英語や中国語、名詞などの格変化によるものも含んでいることを知った。
統語論には、子どものうちに習得する3つのことが関わっており、音による意味識別機能の理解、規則性.法則性の愛着、自己と大人とモノの3項関係の成立がある。私は以前、小さな子どもがティッシュペーパーを箱の中から何枚も続けて出しており注意をしている保育者の姿を見たことがある。しかしこの講義を受けて規則性と法則性の愛着に当てはまると知り、決して悪いことではないのだ分かった。自分の名前を呼ばれて反応したり音を聞いて意味を理解しようとする姿も、統語論を習得するために大切なことだと新たに知ることができた。
〔「音による意味識別機能の理解」、「規則性.法則性の愛着」、「自己と大人とモノの3項関係の成立」の3つが統語論の習得につながっていく自然的なものである、とは、私自身の仮説です。〕
《第9回講義メモ》
はじめに――「他者に向かうことば」と「自己に向かうことば」
【ことばの根本的機能】
前回の講義では、1歳代と2歳代の子どものことばをとりあげ、それらを全体としては「コミュニケーション言語」と特徴づけた。それを言いかえれば、「他者に語ることば」「他者に向かうことば」とも特徴づけられる。
ところで、ことばの機能の根本にあるものを考えてみると、それは「誰に向けられたことばなのか」であろう。
【コミュニケーション言語(他者に向かう言語)と自分に向かう言語】
「誰に向けられているのか」という問いに対して、多くの場合、人は、「他者に向けられている」と答えるであろう(もちろん、家族とか友達とかと言っても、それらは他者に含まれていることに変わりない)。ところが、1つだけそれに該当しないことばがある。それは、「自分自身に向けられたことば」である。
それは、自分とのコミュニケーションといってもよいが、他者とのコミュニケーションとは相当の違いがある。他者とのコミュニケーションとか他者との対話は、そこに他者への「伝達」という要素がつきものであろう。ところが、自己とのコミュニケーションあるいは自己との対話、内的対話には「伝達」は必要がない。では、何があるのか。それは、自分の思考、感情、想像にかかわるもの、言いかえれば、心理過程を担うものということになろう。
【「自己に向かう言語」――発生的には「独り言」そして「内言」】
発生的に見ると、「自己に向かう言語」とは「独り言」に始まり、やがて、「内言」(自己の内部でのみ働く・発音されない・ことば)が担うようになる。
「独り言」は3歳になると目立つようになるので、話しことばの体系が一応のところ獲得される時期に、この新しいタイプのことばが登場することになる。このことばが衰えるのは6歳代のことであり、後に述べることになるが、3歳の危機(発達の節目)において「独り言」が始まり、7歳の危機において「独り言」は衰え、それにかわって「内言」が重要性を増してくるのである。
今回は、こうした「独り言」や「内言」について述べようと思う。
I 新しいタイプのことば――「独り言」の登場と衰退
【「独り言」の機能・役割】
まず、私たち大人も独り言を言うが、どういう場面で言っているのか、また、それはどのような役割を果たしているのかを、考えてみよう。それは他者へのことばとは違って決して「伝達」の役割をはたさないが、無意味で余分な発話とは言えない。そうした発話が担うのは、物事を思い出す、人物を知的に評価する・時には感情的に評価する、これから行う行動を順に言う、計算する、その他であり、「独り言」は心理機能を担っている。
以上は大人の場合であるが、幼児の独り言に関する実験事例からも、それに類したことが言える。ヴィゴツキーの実験を紹介しておこう。
幼児の独り言に関する実験において、ヴィゴツキーは、子どもの活動のなかに何らかの「困難」を惹き起こすモメント(契機)をもたらした。
たとえば、それは次のように記述されている。——子どもが自由に描画している場面で、人為的に色鉛筆などをその場から引き離したもとでの子どもの独り言は、次のように語られている。―「『鉛筆はどこなの。今度は青鉛筆がいる。ないなら、その代わりに赤で描いて、水をたらすよ。黒ずんで青になるから』。これらすべては、自分自身との議論である」(ヴィゴツキー、1934/2001、『思考と言語』第2章第4節、p.58)。つまり、独り言は無意識のうちになされる・自己との対話である。
それを役割・機能の面から捉えれば、独り言は「コニュニケーションのためのことば」ではなく、「思考のためのことば」であり、自由に描画しているときに、色鉛筆などが見つからないなどの難しい状況に直面すると、子どもの独り言はほぼ2倍に増加した(ヴィゴツキー、1934/2001、『思考と言語』第2章第4節、p.58)。
この実験から、「独り言」は、余計で無意味な発話どころか、子どもが思考するためのことばであることが分かる。
小学生でも、算数で難しい計算に直面すると、「ブツブツ、ブツブツ」と何を言っているのかは分かりにくいが、独り言が増大する、という事例もある。
【「独り言」の減少――ピアジェの見解】
大人の独り言は、もちろん、幼児ほど多くない。幼児の独り言はいつまでも多いわけではなく、ある時期に減少していくというのが事実である。
具体的には、子どもの独り言が3歳から7歳にかけて半減すること、しかも、6歳代に大幅に減じることを、事実的に明らかにしたのは、ピアジェであった。
ピアジェの見解は、おおむね、次のように述べている。――子どもの自発的な発話のうちで自己中心的言語(独り言など)のしめる割合は、3歳児において最大であるが、7歳児に近づくとその割合は半減する、というのが中心的な事実である。とくに、「集団的独り言」とピアジェが名づけた状態(たとえば、自由遊びのときの「独り言」)が6歳後半に著しく減少している(Piaget, J.,1923/1948, chapitre II, pp.59-60 『子どもにおける言語と思考』)。
では、なぜ自己中心的言語は凋落するのか。ピアジェは、この独り言の半減を、子ども(の思考)の社会性の増大によって説明しようとした。社会性の増大が自己中心性を減少させる、それがことばの面に現れたのが自己中心的言語(独り言など)の凋落である、と。
子どもの社会性が増大し自己中心性が減少した、それが言語面で現れたのが自己中心的言語である「独り言」の減少である。このように、ピアジェは説明したのであった。
なお、この「独り言」の減少について、ヴィゴツキーはピアジェとはまったく異なる説明をおこなった。「独り言」が減少しているのは、発音されない「内言」が成長しているからである、と。なぜなら、直観的な思考よりもことばによる思考が次第に増大しているからであり、「独り言」も「内言」も、「自己に向けられたことば」、「思考のためのことば」という機能をもつからである。この点については、後ほど、より詳しく述べておこう。
II 新しいタイプのことばを生み出すもの
「独り言」はただそれまでのことばの発達からのみ生まれてくるわけではない。ちょうど、3歳代は「3歳の危機」と呼ばれる発達の節目であり、この時期には、ある意味では、類人猿には見られない心理的特質が人間の子どものなかに顕在化しており、新しいタイプのことばの誕生もそのような「心理的特質」の1つである。
【3歳代――チンパンジーにみられない一群の心理学的特質が顕在化】
3歳代には、類人猿には見られないような、人間の子どもに固有な発達が見られる。それらはことばの習得・体系化と密接に結びついている。
多年にわたりチンパンジーの研究をしている松沢哲郎は、チンパンジーには見られないものとして、①人間が持つようなことば、②ごっこ遊び、③想像する力〔時間的・空間的にひろがっていく想像(イメージ)〕、の3つを挙げている。これらは人間の子どもの場合には概ね3歳代に出揃うものである。
これらは松沢哲郎『想像するちから––チンパンジーが教えてくれた人間の心』(岩波書店、2011年)のを読む限りでは、。
松沢が「ごっこ遊びはない」と述べたくだりを引用しておこう。ここで松沢はチンパンジーの社会性を考えるという文脈で次のように述べている――「人間が4、5歳になって他者の心を理解するまでの過程のほとんどすべてが、チンパンジーにもある。けれども一つ明確にないものがある。それがごっこ遊び(ロールプレイ)や、そこで見られる役割分担や互恵性だ」。〔松沢は社会性の発達の文脈のなかでこのように述べたのだが、「ごっこ遊び」の発達的意味は社会性よりももっと広範囲に及ぶ。“ごっこ遊びはあらゆる発達の傾向を虫メガネの焦点のように凝縮している”––ヴィゴツキー。ことば・想像・感情・知性・自我など〕
この本を全体として見て、より正確に言えば、上記の3つのもの(①人間的ことば②ごっこ遊び③想像力)の萌芽はチンパンジーにも「ある」のだ。たとえば、チンパンジーには、ごっこ遊びの萌芽の一つである模倣はある(ただし視覚的模倣であろう)、人間のことばの萌芽といえるコミュニケーションのための広い意味での「ことば」や簡単な記号の理解はある、短い時間しか働かないが記憶と想像の萌芽はある。
松沢の指摘に一つ付け加えるなら、チンパンジーは鏡に映った自分を自分であるとわかるという自我の萌芽はあるが、そこから10年をかけて「自分を知る」(自己意識)ということに至る人間のような自我はない。3歳代の「自我の芽生え」は人間の子どもに固有な4つ目の特徴である。
【3歳代における「自我の芽生え」】
この時期の「自我の芽生え」とは何かを正確に認識するためには、「7歳の危機」「13歳の危機」と言われるものと対置することが必要である。これは後でおこなうが、ここではまず、一般的特徴に限って述べておこう。
まず、3歳は「反抗期」(13歳は「第2反抗期」とも呼ばれる)と言われるが、それは「独特な反抗」を表している。普通に考えると、何かやりたいことがあるのに、それを大人が遮ったので「反抗」する、「強情」をはる、「頑固」になる、というように捉えられる。それも3歳児にはあるが、もっと特徴的で独特な「反抗」とは、大人が「〜しなさい」と言ったので、本当は「したいこと」なのに「しない」、という「反抗」である。
ここで重要なのは、そのように「反抗」する子どもの行為・発話の動機である。普通は動機は事柄やモノにある。つまり〜をしたい、このモノを扱いたいという動機である。ところが、この「反抗」においては、動機は事物・モノから人間に移っている。大人がこうしなさいと言ったのでしない、という具合に、動機はその大人に〔反対することに〕ある。
この時期には、そのような独特な「反抗」を表す遊びのようなものさえある。子どもは「白いハンカチ」に対して「黒いハンカチ」と言う。それはまるで遊びであるかのようである。このハンカチは「黒いね」と大人が言えば、「白いやんか」と返ってくる。これなどは、大人の反対を言うことが面白い、ということを示している。
もう1つの大きな特徴は、上記のような「反抗」のなかには確かに「自我」があるのに、子どもは自分に自我があることを認知していない、ということである。これは、13歳の危機との大きな相違である。
III イメージの遊びのなかで発達することばの機能
【虫メガネの焦点のように】
虚構場面(イメージされた場面)を伴う遊び(ごっこ遊びなど)は、虫メガネの焦点のように、発達のあらゆる傾向を凝縮している――というのは、ヴィゴツキーのことばである。
ここで言われている「発達のあらゆる傾向」とは、あらゆる心理機能や心理過程を表しており、そこでは、当然ながら、ことばの機能の発達も含まれている。それについて、考察してみよう。
【事物・モノとことば――事物・モノからの語の解放】
事物(モノ)と語との関係を取り上げてみると、おおよそ2歳代の子どもは「状況拘束性」のなかにあり、ことばによる誘発というよりは、彼のいる状況(視覚的な場)のなかにある事物に誘発されて行為する。階段があれば登ろうとするとか、鈴があると振って鳴らそうとする、という事例が、それをよく表している(ヴィゴツキー、1933/2012、p.153)。いわば、“事物の誘発力”である。これがはっきりと見られるのは、2歳代のことである。
子どもがもう少し大きくなり、3歳を超えた幼年期にはいると、対象(モノ)と語との関係は独特さをおびてくる。語は、対象から離れて、他の対象の名称となりうる(いわゆる見立ての成立)が、まだ対象の性質から完全に分離されたわけではなく、両者の結びつきが保たれている。この点の説明に、ヴィゴツキーはある実験的観察を紹介している。
――雌牛と犬を置き換えたあとでの実験者の質問と子どもの解答である。「『犬に角があるなら、この犬はミルクを出すの?』––と子どもに尋ねる。––『出すよ』。『雌牛には角があるの?』––『あるよ』。『雌牛は犬のことだから、じゃあ、犬には角があるの?』––『もちろん、犬が雌牛なら、雌牛と呼ばれるなら、角もなくちゃいけない。雌牛と呼ばれるってことは、角もなきゃいけないってこと。雌牛と呼ばれる犬には、小さな角が絶対になきゃいけない』」(ヴィゴツキー、1934/2001、『思考と言語』p.374)。このように、この時期の子どもは、名前の転移を受け入れながらも、まだ語は対象の性質から完全には分離していないのである。
イメージを伴う遊びにおいて、事物・モノからの語の解放がなしとげられていく。しかし、その始まりにおいては、小石がお菓子となるように、小石という他の(お菓子とは違う)事物・モノの支え、「はい、お菓子、どーぞ」というような行為の支えが必要である。語の完全な解放(語の自由な操作)が可能になるのは、おおむね7歳の危機よりも後のことであろう。
【他者の役を実現することば――ことばの一層の自由の実現へ】
イメージを伴う遊びのなかでなされるのは、ある事物・モノを他の事物・モノとして扱うだけではない。遊び手たちが、自分以外の何者かになる、ということをしている。ここに、他者の自己化(他者を自分のなかに取り込むこと)があり、同時に、自己の他者化(自分を他者のように表現する)がある。ここでのことばは、自分は自分のままで事物・モノとことばとの関係を自由に変更すること(自由に見立てること)よりも、一層のことばの自由が実現されている。
簡単なモノの見立てらしきものはチンパンジーにも見られることがあるようだが(木片を小猿のように抱いているように見える。想像の萌芽)、他者の自己化と自己の他者化とを実現するようなことばの使用は、もはや、類人猿には到達しえまい。ここにも人間に固有な心理的特質が明瞭に現れている。
IV 3歳、7歳、13歳の危機
【ヴィゴツキーにおける「3歳、7歳、13歳の危機」】
「3歳の危機」の時期:ヴィゴツキーによれば、「自我はあるのだが、その子どもは自我があることを知らない」。つまり自己意識というものはまだ成立していない。敢えて言えば、そのような自我は、ただ自我があるという意味で、「即自的」な自我である。自己意識は形成されていないが、他の動物にはないような形での意識は形成されはじめている(話しことばの体系が一応のところ成立している時期と一致する)。
「7歳の危機」の時期:ヴィゴツキーによれば、内面と外面が「矛盾」するような振るまいを、この時期の子どもはしだす。彼の自我はすでに3歳児の自我とは違う(おそらく6歳代に内言が増大することがこのことに関与しているであろう)。彼は自分の自我を意識しているので、それとは「矛盾」する外面をつくりだすことができる(内面とは異なる「ひょうきん」な外面など)。しかし、まだ13歳の危機における自我のように、自己の内面のなかには入り込まない。敢えて言えば、この自我は「対他的」な(他者に対する)自我である。
「13歳の危機」の時期:ここにおいて、自我は自己によって意識される自我となり、本来的な自己意識が成立する。しかし、3歳の時期の意識の形成の始まりに匹敵する、13歳の時期の自己意識の形成の始まりであり、それは、かなり長期にわたる過程のなかで継続される。その自我は、「対自的」な(自分にとっての)自我である。
自己意識とは:直接的には、自分の自我を認識するという意味であるが、そのことを含めて、少なくとも3つの側面が考えられる。①自己の認識・理解、②自己との関連における(自己とかかわらせた)他者の認識・理解、③自己との関連における(自己とかかわらせた)周囲の事柄や世界の認識・理解、の3つである。①だけを自己意識と考える人もいるが、それだけでなく、他者と私の関係、世界と私の関係という形で、他者や周囲の事柄さらには世界を内面的に捉えることができるようになることに、自己意識の主眼があるように思う。
「即自的」自我、「対他的」自我、「対自的」自我について:もともとは哲学者ヘーゲルの概念であるが、3歳、7歳、13歳の危機のそれぞれにおいて、上記の3つの自我が順次、生まれてくると説明できる。
これまでに述べたように、ただ私には自我があるという状態、しかし、それがどのような自我であるかを認識していない状態、あるいは、そのような状態のなかにある自我を「即自的」自我と呼ぶ。したがって、私の自我はどのようなものかという省察や考察や認識はない。したがって、ある時には「自分で!」と言い張って、自分ですることを譲らないこともあるし、本当はしたいことなのに大人が「〜しなさい」と言ったのでしない、ということもある。
これは他の動物には見られないものであり、同時に、それまでに蓄積されてきた「共同注意フレーム」「3項関係」の狭さ(大人のあまりにも先回りした世話)を打ち壊し、そのフレームと関係のなかにおける対等性を打ち立てようとしているかのようである。
7歳の危機において発生する「対他的」自我はすでに自分を意識しているが(「即自的」自我との違い)、それは限定的であって、自分のなかに入り込まず、つまり、自分とはどのような人間かの考察にまではすすまずに(「対自的」自我との違い)、他者に対してのみ自分を示そうとする。自己の考察へは進まないので、まるで自分を装っているかのように他者にふるまうことさえある。
「自己との関連における(自己とかかわらせた)」認識や理解ということが自己意識成立後の認識・理解の、以前にはなかった特徴である。このことを、以前の「即自的」「対他的」に対して「対自的」という。このような意味において自己意識が形成されはじめるのである。(この点についての詳細は第14回講義で述べようと思う)。
【それらの「危機」とことばの再編】
これまでの講義で述べてきたような、発達過程におけることばの事実を拾い集めてみると、上記の3つの危機は、ことばの再編を行っていると考えることができる。ことばの再編は、危機に先行する形で、あるいは、危機の渦中で、行われている。
喃語と初語とのあいだの沈黙、初語における意味の般化と分化は【1歳の危機】に関連して創発し、その後、語の意味が安定するにつれて、事物と語との癒着、統語論などの文法習得がコミュニケーション言語を支えるようになる。そこから新しいタイプのことば(独り言)は【3歳の危機】に関連して、自己に向かうことばとして誕生する。まだ自己に向かうことばは内言のように安定していないので、イメージのある遊びの形をとって事物・モノからの語の解放、ことばの一層の自由が進行する。これは、「状況拘束性」からの脱出であるとともに、やがて内言を準備するようになる。こうして【7歳の危機】を迎えることになる。【ヴィゴツキーが極めて骨太く指摘しているように、「遊びは、学齢期になると、内的過程に、内言・論理的記憶・抽象的思考に移行する。」ヴィゴツキー『「人格発達」の理論』p.158】
内言は「自己にむかうことば」であるので、伝達機能ではなく思考などの心理的機能を果たすものである。だが、内言はまだ自己の内面の省察に進むまでには至っていない。したがって、自分のなかに知の軸になるもの(たとえば自分流の世界観など)をまだ形成していないので、知は事物と癒着している。学校教育を通して多くの知識を得ているが、まだ自分のなかの軸にそって蓄えられるには至らない。この軸こそ自己意識であり、それによって、事物に癒着していた知をもぎとって自分の方に持ってくる。このような自己意識を形成し始めるのは、【13歳の危機】においてである。
ことば・語を事例として考えてみると、「対自的」なことばとは、自分に対することば(自分に語ることば)、つまり、内言のことである。
V 内言について
【独り言の減少についてのヴィゴツキーの見解】
すでに紹介したように、ピアジェの考えによれば、子どもが自己中心性を低下させ社会性を増大させているが故に、独り言は減少している。
それに対して、ヴィゴツキーはまったく異なる見解を表明している。私は、ヴィゴツキーの考え方はより深い、と思う。
具体的には、ヴィゴツキーは次のように考えた。――自己中心的言語(独り言など)の半減という事実の核心を、ピアジェが言うような社会性の増大というよりは、内言(聞こえない・自己のための言語)への成長を表したもの、と考えた(ヴィゴツキー、1934/2001、『思考と言語』第7章)。
ヴィゴツキーの死後30年近く経って、ピアジェは、ヴィゴツキーが自己中心的言語(独り言など)に着目し、それを基盤にして「内言」が成長すると述べていることを知り、基本的には、そのことに賛意を表している。
それは次の著作のなかにある。ピアジェは、1962年に英語版として出版されたヴィゴツキーの『思考と言語』にコメントを寄稿した。そのなかで、それまでにはピアジェが使用していなかった「内言」の概念に次のように言及している。
――「ヴィゴツキーは、私がうまく理解しているとすれば、子どもの知的自己中心性の観念については私と一致していないが、彼は、私が自己中心的言語と呼ぶものの存在を認め、そこに、後続する──しかも、論理性とともに、自閉性の終焉に役立つ──内的言語の出発点を見ている」(1962 / 1997, p.502)。
分かりやすく言えば、ピアジェが用いた「自己中心的言語」の概念を、ヴィゴツキーは使い、彼はそこから「内言」が後続してくると考えている。この「内言」は「論理的思考」や幼い時期の「自閉的思考」の解明に役立つものである、と。
こうして、独り言は子どもの社会性の増大のなかで減少するとピアジェが考えたことは表面的な認識であり、その奥には、内言の成長が潜んでいるというヴィゴツキーの考えに、ピアジェも賛同したと考えてよいであろう。
【内言の構造について】
ことばのもっとも根本的な機能は、誰に向けたことばか、という点にある。独り言も内言も他者に語ることばではない。したがって、独り言も内言も、自己に向けられたことばである。内言の基本的な機能は、自己に向けられたことば、という点にあり、したがって、伝達ではなく思考を、より広く言えば、心理的機能を担うものである。このことはすでに述べておいた。
ここでは、内言の具体的な姿について、構造の面から明らかにしておきたい。
内言の形相的な面:ことばの形(形相phaseとは「月の満ち欠け」を表す語である)からすると、内言は発音のないことば、主語が要らないことば、述語を短縮したことば、甚だしくは語のかけらである。内言は根本的には他者への伝達が必要なく、自分に言い聞かせればよいということばなので、最大限に短縮され圧縮されたことばということになる。
他の種類のことばと比べてみると、ことばの形相的側面からすると、書きことば―話しことば―自己中心的言語(独り言)―内言という順に、詳細で展開的なことばから短縮されたことばへ、さらには、語のかけらへ、と並べることができる。書きことばと話しことばは他者に向かうことばであり、どちらも外言なのであるが、「話しことば」は、眼の前にいる人に語ることばであり、その人は自分と同じ状況のなかにあり、話題を共有しており、相手と私はそのお互いの発話が次の発話の動機をつくりだしているため、ときには、単語ひとつで間に合うことさえある。他方、眼の前にいない人に対して、あるいは、不特定多数の人たちに対して分かるように語る「書きことば」は「話しことば」よりも遥かに詳しいことばである。独り言と内言とは自己に向かうことばであるので、様々な省略や短縮が可能となる。
内言の形相的な面は、音がなくなり、主語が省略され、最大限に短縮されるという意味で、音声論では「無音のことば」、統語論の面では「絶対的述語主義」、語彙論においては「語のかけら化」を特徴としている。
内言の意味的な面:内言の形相の面と意味の面とは、相互に依存しつつ相互に対立する。形相が縮小するのとは逆に、意味は肥大化するのである。
そのメカニズムと考えられるのは、語からの意味の流出と他の語への意味の流入であろう。たとえば、話しことばを例にとれば、「スマート」と「フォン」の2つの語から「スマホ」という1つの語ができることは、このメカニズムに則っている。「全然」という語は以前には否定文に使われていたが、今日では肯定文にも使われ、「全然よくない」だけでなく「全然いいです」も普通につかわれている。意味の流入の事例であろう。このような話しことばにおいて可能になる語と意味との動的な関係は、内言ともなると、音を失い、主語を失い、述語も部分だけですみ、ましてや単語はそのかけらだけで事が足るのであるから、語と意味の関係もいっそう動的となり、意味の流出・流入が大きくなる。
その点について、ヴィゴツキーは見事な比喩を用いている。内言における形相と意味との関係は、小説におけるタイトルと内容との関係に似ている、と。もちろん、この場合、タイトルは形相であり、内容は意味である。デレビドラマでも、漫画でも、映画でも、小説でもよい。あえて流行したテレビドラマ、漫画を例にとれば、「東京タラレバ娘」「偽装不倫」「逃げ恥」というタイトルを見ただけで、それぞれの内容が思い浮かべられる。それは、短いタイトルに膨大な内容が詰まっているからであろう。「逃げ恥」はタイトルそのものを短縮したものであるので、そのタイトルと内容との動的関係はいっそう内言における形相と意味との関係に近いと言えるであろう。
こうした内言の形相・意味の両側面の相互依存的であるとともに対立的な運動を把握したことは、ヴィゴツキーの独創であった。
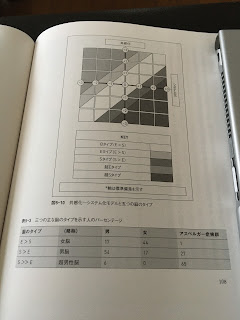
コメント
コメントを投稿